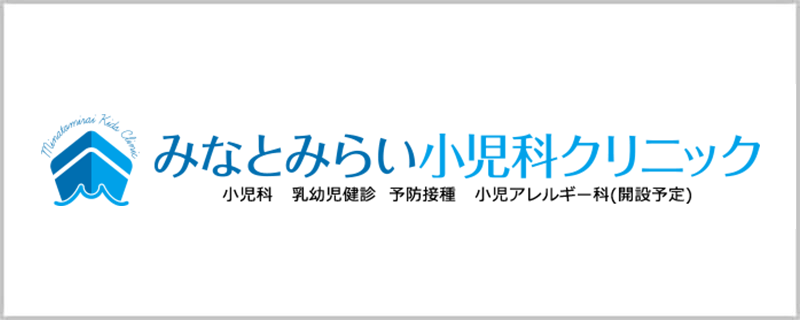吃音(きつおん)とは?子どもが発症する原因や対処法を紹介~前編~
こんにちは。ONEPLAY.GIFTED 横濱元町教室です。
子どもが成長して言葉を話すようになった時、あるいは同年代の子供が上手に話せている時に、「うちの子は、なかなかうまく話せていないかも」と思ったことはありませんか。今回は、約100人に1人いるとされている「吃音」(きつおん)の原因、種類や症状などをご紹介します。
《 吃音とは 》
吃音とは、言葉の滑らかさ(つまり、流暢な発話の表出)が妨げられる症状のことをさします。音声言語の症状のみでなく、体の一部がこわばったり、部分的に力が入ることも吃音の症状の一部です。また、身体上の合併症などが存在する可能性もあります。
《 吃音と発達障がいの関係 》
吃音は、日本国内における発達障害者支援法という法律で発達障がいと定義されています。
《 吃音の発症原因 》

吃音の発症原因は特定されておらず、様々な要因が影響しあって生じているといわれています。性格や心理的なストレス、育った環境や育て方は発祥の直接の原因ではないといわれているため、例えば人前で話すことへの不安、不安の強さなどにより発症することはありません。
《 吃音の生じる人の割合 》
約100人に1人、1%程いるとされています。
つまり、日本では約126万人いると推定され、世界では約7700万人いるとされています。
《 発症年齢 》
吃音の発症年齢は、2歳から5歳頃と言われています。発症率は少し高く、5%の割合で発症するとされています。
《 吃音の種類 》
吃音には主に3種類あります。
①連発(言葉の繰り返し)
「わ、わ、わ、わたしの、な、な、な、なまえは、い、い、い、・・・」
②伸発(ことばの引き延ばし)
「あーりがと」「こーんにちは」
③難発(阻止・ブロック)
「・・・い・い・・・ます」
このような吃音の典型的な症状3つのことを、「吃音中核症状」と呼びます。
しかしながら、この吃音中核症状は氷山の一角にすぎず、一側面にすぎません。先ほど挙げた吃音の症状は目に見えるものなので、そこに注目しがちですが、その氷山の下にある問題について考えていかなくてはいけません。

実際に吃音のある人は、吃音症状に対して不安や恐怖、またはストレスを抱えてしまうため、話すことに自信が無かったり、自己効力感が低下していきます。そうなると、うつ、不登校、引きこもり、社会不適応、就業困難などの深刻な状態につながることがあります。
いじめやからかい、悪口など、周りの人の反応により深刻化の恐れがある吃音。次回は、子どもの吃音が進展するとどうなるのか、どのような治療法があるのか対処法をご紹介します。
#吃音 #発達障がい #子供 #成長 #発達
《記事を書いた人》
坂本 卓生
社会福祉士、介護支援専門員
20年近く児童、高齢、障がい福祉に社会福祉士として携わり、これまでに多くの人たちのサポートを実践。自身も2児の父親として子育てに奔走中。現在ONEPLAY.GIFTEDにて子どもたちや保護者様の相談支援を行いながら、専門職育成にも力を入れ活動中。
————————————————
ONEPLAY.GIFTED 横濱元町
〒231-0861
神奈川県横浜市中区元町3-130-1 MID横濱元町2F-C
※無料体験はこちら⇓
https://oneplay-gifted.jp/kids/
※採用情報はこちら⇓
https://oneplay-gifted.jp/recruit/